※当サイトには広告が含まれています
※またネタバレほどの内容開示はないですが、一部の内容公開を含みます
初恋

淡い思いを連想するタイトルとは違い、非常にセンセーショナルな作品に仕上がっています。
※本ページの情報は2025年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
センセーショナル

2018年刊行の作品です。
センセーショナルな導入部分にとてもインパクトを感じました。
「映画の序盤はいかにもフィクションで台詞めいているな」と、生意気にも感じましたが、観ていくうちにとても引き込まれていく、良い作品でした。
冤罪、無意識、鬱憤

日常に潜む小さな冤罪の数々。
黙殺されている、耐えるべきなのかも分からない心に痛いできごと。
それらは大昔から続いていることで、ごく当たり前かのように日常にあるものであると思います。
日常で、特に仕事などでストレスを感じることは、誰にでもあると思います。
かえってそれがやりがいや、自分の成長につながることも往々にしてあると思うんです。
私は、特に仕事の時に発される人の怒りの感情というのは、その瞬間のできごとに対してだけではなく、
その人が日ごろから抱えてきた鬱憤(うっぷん)や、変えられない過去に対する痛みも無意識に織り込まれている気がします。
陰と陽、贖罪

この作品の原作者である島本理生さんは今作で直木賞を受賞しており、また他の作品で芥川賞候補にも挙げられた、
陰と陽の両面に対して作品へ想いを込められる作家さんだと思います。
日常のあらゆるできごとに対する解釈―できごとを、良いことと悪いことのどちらだと捉えるかは、その瞬間の自分の状況・環境・感情次第だと思うんです。
だからこそ黙殺されるし、愛もあるからこそ後で笑い話にもできるんです。
良くも悪くも、人間はとても器用な生き物です。不器用さもいつか善行だったと昇華できるように。
小さな小さな日常における過ちは、自分の無意識下で留まり、後に贖罪として人のためになるような行動、言動に移っていくのではないでしょうか。
昔不良だった人が、大人になって多くの人を救うようなストーリーのように。
被疑者である環菜さん(映画で演じるのは芳根京子さん)は、極端に言えば、小さい頃から家族の奴隷だったように思えます。
父親への恩があるからと言いなりになり、家族以外の第3者から見れば異常だと思いをさせられて。
ただ、このようなできごとは日常にも多々あると思うんです。
こうしたフィクションの作品というのは、日常のできごとを大きく大げさに飛躍させたものだと思っていて。
大なり小なり似たようなできごとは起こってしまっていると思うんです。
人の価値観は本当に十人十色なので、きっちりとその人が不快にならないようにするのは難しいでしょうが。
ちなみに私はこの作品をVODとオーディオブックで鑑賞しました。
迦葉は映画では善良な本音の部分の出る量が少なく感じますが、オーディオブックでは根が優しいことが序盤から聴き手に伝わりやすくなっています。
そして環菜さんは、映画では情緒不安定さが目立ちますが、オーディオブックではおおむね冷静さを保っているように捉えられます。
※本ページの情報は2025年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
愛情と惰性、堕落
どれだけこの記事を読んだ方に伝わったかは分かりませんが、やはり現代への色んな問題提起をはらんでいるからこそ、ドラマ化も映画化もされたのだと思います。
愛情と惰性・堕落とをどうか、履き違えませんように。
また追記したいことがあれば付け加えていきたいと思います。
あまりシリアスになりすぎるのも身体にはどうかと思うので、濃いめのバラエティーなど見てバランスを整えましょう(笑)。
即座に追記(笑)
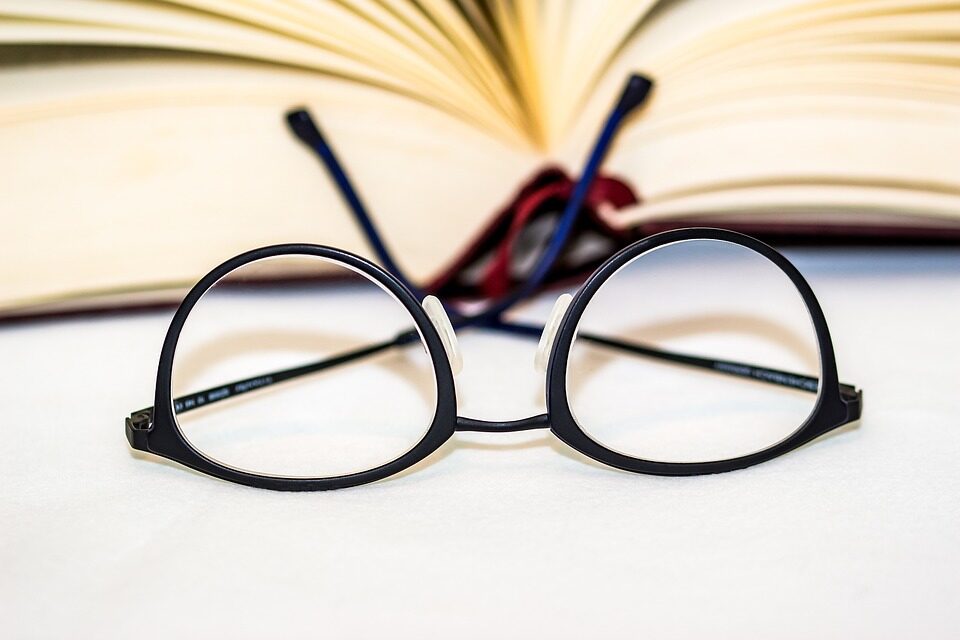
こうした原作のある作品というのは1つの世界観にまとまりがちです(当たり前かもですが)。
しかし現実は、一人一人の様々な世界観―価値観の上に、成り立っています。
そんな中で毎日、普通に衣食住があり、安心して暮らせる環境があることは、基盤として人々の愛があってこそだと思うんです。
当たり前の日常の上に多様なサービスがあり、それを活用できて喜びあえる関係性があるというのは、愛なしではできてこないと思います。
これは素晴らしいことです。
嫌なこともたくさんあるかもしれませんが。
私たちは、嫌なこと自体を相手にするのではなく、無意識下に起こってしまう、自分や他人との齟齬―食い違いと日々闘うべきなのかもしれません。
人間は弱いし、忙しく一瞬一瞬を生きたり、かと思えばダラダラと生きてしまう生き物です。
動物だって同じ生き物なので、人間と同じような生き方をする側面もありますが。
どんなことがあってもその一瞬のできごとは良くも悪くも過ぎ去り、忘れ去られます。
人はきれいさも汚さもあります。間違ったことやずるいこともしてしまいますが、素晴らしい一面もたくさんあります。
どうか自分から愛を持って生きてみてください。
今まで愛を感じたことがなくても、人はみんな鏡だから、そこで初めて愛を感じられるかもしれません。
物語の終盤で、環菜さんの自傷行為における伏線はつながります。他の事実も垣間見えます。
フィクションは現実の飛躍と述べましたが、この作品を通して、自傷行為をする人の気持ちが少し理解できた気がします。
現実では直接相手の苦しみについて理由を聞き出すことは難しいことが多いと思います。
そうした意味では、こうしたフィクション作品は、似たような思いをしている当事者にとっても、受け手にとっても救いになるでしょう。
「それでも罪は罪」といったような終わり方をすることも、この作品の問題提起を色濃く感じさせる要因となっているのではないでしょうか。
あいまいなアイデンティティの中で

モラトリアムな時期までは、どうしても感情を大人に委ねざるを得ないことが多いかと思います。
気づかない内に選択権を親に譲る習慣がついてしまうんですね。
人間にはどうしても強者と弱者、優劣の関係が生まれがちです。
親と子となれば、なおさらのことでしょう。
昨今の親ガチャという言葉は言いすぎかもしれませんが、
親と子という関係性には、
良識のある責任と、
友好的な均衡が不可欠です。
それらをいつまでも穏やかに保ちたいものです。
初恋をさがして

小説からドラマ・映画と表現の場を移して展開されるこの作品は、どこか人の心に刺さるものがあるのでしょう。
暗闇の中でも必ず光は射して射しています。
今は見えなくても、必ず射しこむ日は来る。
そして思えば遠い記憶にも、あなたの初恋は、光が射しこむ瞬間はあったはず。
今度はあなたから現在、未来に光をかざして。
どうか光あふれる未来をさがし出してください。
※本ページの情報は2025年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a3322c1.cc77ce23.4a3322c2.6eff5dca/?me_id=1220950&item_id=14053742&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneowing-r%2Fcabinet%2Fitem_img_1515%2Fbibj-3483.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49ea31ac.e70d80de.49ea31ad.54f2cef0/?me_id=1213310&item_id=19870866&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4356%2F9784167914356.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)